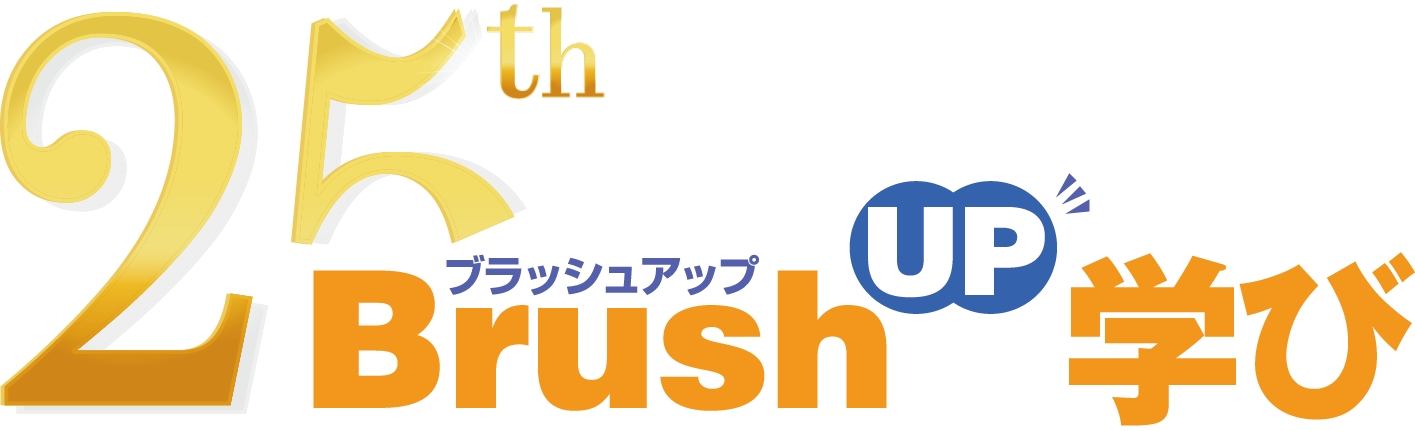1次試験では「経済学・経済政策」「財務・会計」「企業経営理論」「運営管理」「経営法務」「経営情報システム」「中小企業経営・政策」の7科目を受験します。(択一式)
合格基準は総得点数の60%以上、かつ1科目でも40点未満のないこととなります。合格率は例年20%前後で推移しています。
また、1次試験不合格でも60点以上得点した科目は科目合格となり、合格年度含め3年間有効となるので、翌年と翌々年は当該科目が免除となります。


合格には「全科目の総得点が60%以上であること」「1科目でも40点未満がないこと」という2つの要件があるため、どの科目でも平均して60%ほどの点数をとれることが必要になってきます。不得意科目の点数を得意科目の点数で補う、という方法もありますが、苦手科目で40点未満をとってしまうとその時点で不合格になってしまいます。
科目には理解が必要、暗記で事足りる、といった必要なスキルから、要する勉強時間、点数の取り易さなど様々な特徴があります。これらの特徴を把握し、試験までの期間にあわせて効果的な学習スケジュールを組むのは、独学だとなかなか困難です。
それぞれの科目の特性に合わせた授業を受けることができ、なおかつスケジュールについても管理してもらえるスクールに通うとよいでしょう。

1次試験が8月、2次試験が10月と期間が2ヶ月しかないため、1次試験受験後に2次試験対策を始めるのでは一発合格は難しくなります。そこで必要となってくるのが「1次試験と2次試験を融合的に対策する」ということ。1次試験の中でも2次試験に関連性が高い科目と低い科目があります。そこで2次試験との関連性が高い科目に注力し、筆記試験にも対応できるよう、単なる暗記ではなく本質的な理解をした上で択一の問題を解いていく力をつければ、実際に記述対策を始める際スムーズに移行することができます。
逆に関連性が低い項目はあまり時間を取らず、択一のみ解ける力をつけていくといったようなメリハリをつける必要があります。


中小企業診断士は、1次試験は合格科目が3年間有効となっているため、1年目では3科目受験・2年目は4科目受験する、もしくは一気に7科目受験し、落ちた科目は来年再受験する、といった長期スパンで計画されている方もいるかと思います。しかし、2次試験に関連する科目を先に合格した場合、翌年もしくは翌々年の2次試験受験の際、再度学習し直す必要があります。それよりも1次試験に7科目一気に合格し、すぐに2次試験に臨んだ方が1次試験に学習した知識が残っているため、合格しやすいと言えるでしょう。
また、1次試験を合格すると、合格年度の翌年の2年間、2次試験を受験することができますが、この場合も知識を保持するのが難しいので、1次合格年度に2次も合格するのがベストです。
受験に対するモチベーションの維持も重要な問題になります。期間が延びれば延びるほど、モチベーションを保ち続けて勉強をすることは難しくなります。
よって中小企業診断士に合格するためには、なるべく短い期間でいかに効率的に学習するかということが大切になってきます。自分ひとりで戦略的な計画をたて、忠実に実行していくのは思った以上に難しいものです。積極的にスクールを利用するのがベストでしょう。