独学で日本語教師を目指すことはできるのか?
日本語教師は独学でも目指すことが可能なのでしょうか?結論をいうと、独学でも日本語教師になることができます。
実は日本語教師には必須となる学歴や資格はありません。とはいえ、実際に働く際には専門知識や経験、資格などが求められることが多いです。その中でも、国家資格の「登録日本語教員」は認定日本語教育機関で働く際に必要となる資格です。
「登録日本語教員」の資格は、独学で取得することも可能です。具体的な方法をご紹介します。
独学で登録日本語教員を目指すなら「試験ルート」
日本語教師の国家資格である「登録日本語教員」を取得するためには、基本的に「養成機関ルート」と「試験ルート」のどちらかで目指す必要があります。
そのうち、独学で目指すなら「試験ルート」を選択しましょう。
関連記事 日本語教師の国家資格「登録日本語教員」とは?資格の取得方法や第1回の試験予定、経過措置を解説!
登録日本語教員の試験ルートとは?
登録日本語教員の試験ルートとは、養成機関などに通わず、日本語教員試験(基礎試験・応用試験)を受験し、合格後実践研修を修了することで資格が取得できるルートです。
試験ルートは独学で受験するものですが、文部科学大臣の登録を受けた登録実践研修機関で実践研修を受けなければいけません。いわゆる教育実習を行うため、試験に合格した後、指定機関に通ってカリキュラムを修める必要があります。
尚、登録実践研修機関は日本語教育機関認定法ポータルで調べられます。ご自身が通いやすい学校はどこか、事前に確認しましょう。
日本語教員試験(基礎試験・応用試験)について
日本語教員試験は、登録日本語教員の資格を取得するための試験です。試験ルートでは基礎試験と応用試験の両方に合格しなければなりません。(養成機関ルートの場合は基礎試験が免除され、応用試験のみの合格)
受験にあたり、年齢や学歴、国籍などの条件はないため、誰でも目指せる点が特徴です。試験範囲は、文部科学省が公開している「登録日本語教員 実践研修・養成課程コアカリキュラム」の養成課程コアカリキュラムにおける必須の教育内容から出題されます。
基礎試験では基礎的な知識・技能が区分ごとに出題されます。応用試験では基礎的な知識・技能を活用した問題解決能力を測るために、教育実践と関連づけて区分横断的に出題されます。
| 基礎試験 | 応用試験 | |
| 試験時間 | 120分 | 読解:100分 聴解:50分 |
| 出題方法 | 選択式マークシート(1問1点) 100問 |
選択式マークシート(1問1点) 読解:60問 聴解:50問 |
| 出題内容 | 日本語教育に必要な基礎的な知識・技能を問う。 1、社会・文化・地域 2、言語と社会 3、言語と心理 4、言語と教育(教育実習を除く) 5、言語 |
基礎的な知識・技能を活用した問題解決能力を問う、領域を横断した出題。 聴解問題では、日本語学習者の発音や教員とのやりとりを聞いて、実際の指導に即した問題が出題される。 |
第1回日本語教員試験
2024年11月17日(日)に第1回日本語教員試験が実施されました。試験結果は次の通りです。
| 基礎試験・応用試験受験 | 応用試験受験 (基礎試験免除) |
全体(試験免除者も含む*) | |
| 受験者数(人) | 3,947 | 7,750 | 17.655 |
| 合格者数(人) | 366 | 4,727 | 11.051 |
| 合格率(%) | 9.3 | 61 | 62.6 |
*現職者向けの経過措置対応では、基礎試験と応用試験の両方を免除されるルートもある。
試験ルートでの合格率は次の通りです。
| 受験者数 (人) |
基礎試験 合格者数 (人) |
応用試験 合格者数 (人) |
合格率 (B/A) (%) |
| 3,681 | 323 | 322 | 8.7 |
注:基礎試験の不合格者は、応用試験を受験しても採点されないため除いている。
基礎試験・応用試験の両方を受験した人の合格率は9.3パーセント、試験ルートの合格率は8.7パーセントです。いずれも合格率は10パーセントを切っており、難易度が非常に高いことがわかります。
また、全体の受験者数(17.655人)のうち、試験ルートの受験者(3,681人)は2割程度です。主に現職者向けの経過措置対応を利用する受験者が8割近いため、試験ルートでの受験は少数派となります。
独学で日本語教師の資格取得を目指すメリットとデメリット
メリット

独学で日本語教師の資格取得を目指すメリットには、以下のようなものがあります。
費用が安い
独学で日本語教員試験の合格を目指す場合、かかる費用は試験対策に必要な教材費や受験費用、実践研修費用、資格の登録手数料です。
一方、養成機関ルートは学校に通うための学費が必要です。給付金制度や割引制度で負担額が軽減される場合があるものの、養成機関ルートは金銭的負担が発生します。そのため、養成機関ルートに比べて試験ルートは費用を安く抑えることが可能です。
かかる費用の例
| 養成機関ルート | 試験ルート |
|---|---|
| ●養成機関の学費…40万円~80万円程度 ●別途実践研修を受ける場合…5万900円~20万円程度 ●応用試験の受験費用…17,300円 ●その他テキストや講座代 ●登録手数料…4,400円 ------------------- 合計 47万円~100万円程度 (+テキスト・講座代) |
●基礎試験・応用試験の受験費用…18,900円 ●実践研修…5万900円~20万円程度 ●その他テキストや講座代 ●登録手数料…4,400円 ------------------- 合計 7万4千円~23万4千円程度 (+テキスト・講座代) |
注:養成機関や実践研修の費用は学校によって異なるため、目安の金額です。
実践的スキルはプロから学べる
日本語教師の資格に関する旧制度では、独学で日本語教師を目指す場合に、実践的なスキルを学ぶ機会が用意されていませんでしたが、新制度では独学であっても登録実践研修機関で研修を修了することが義務づけられています。
したがって、独学であっても実践的スキルはプロの講師から学べることが、メリットの1つとなるでしょう。
参考 文部科学省「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令」
学習期間によっては最短期間で国家試験を目指せる
養成機関ルートではカリキュラムの都合上、学習期間が設定されています。6ヶ月から1年ほどかかるコースが多いです。出願時には、養成機関を修了見込みでも日本語教員試験を受験できますが、合格しても仮合格扱いになってしまいます。例えば、試験実施が2025年11月だった場合、2026年4月末までに修了証書を提出する必要があるため、逆算して養成機関に通わなくてはいけません。
学習期間が1年間のコースを受講する場合、2026年4月末までの修了を目指して、遅くても2025年4月には養成機関に通う必要があります。そのため4月を過ぎてから1年コースの養成機関に通いたい場合は、11月の試験を見送ることになってしまいます。
しかし、試験ルートでは自分のスケジュールで学習を進められるため、2025年4月を過ぎていても11月の受験を目指せます。
学習期間は十分に確保することがおすすめですが、タイミングによっては養成機関ルートよりも早く資格を目指すことが可能です。
デメリット
独学のデメリットは、すべてを自分でおこなう必要があること、そして授業の実践力がつきにくい点が挙げられるでしょう。
基礎試験を受験しなければいけない
養成機関ルートでは、基礎試験が免除されて応用試験のみの受験となります。しかし、試験ルートは基礎試験と応用試験の両方に合格しなければならず、受験のハードルが上がります。
限られた学習時間の中で両方の試験勉強をするのは、負担に感じる方も少なくないでしょう。
試験の合格ラインは後述しますが、基礎試験は出題内容の各5区分で6割程度の得点および、総合得点で8割程度の得点というラインが定められています。つまり基礎試験では5区分の内容をまんべんなく身につけることが求められるため、早めに苦手分野の克服に取り込むことがおすすめです。
教材準備や学習計画をすべて自分で進める必要がある
独学の場合、教材準備や学習計画をすべて自分で進める必要があります。
大学やスクールの講座と違いカリキュラムがないため、情報を集めて自分に合った教材を選び、学習計画を作り、モチベーションを維持しながら学習することになります。
学習の適切な順序を教えてくれたり、近年の出題傾向に合わせた課題を出してくれたりする人がいないため、自分でそれらを模索する必要もあります。
参考テキストが少ない
登録日本語教員の資格は2024年に新設されたばかりであり、日本語教員試験の実施回数はまだ少ないです。そのため、市販の参考テキストや過去問があまりありません。
そこで、日本語教員試験の出題範囲と重複するところが多い「日本語教育能力検定試験」が参考になります。
こちらは1963年から続く資格試験のため、日本語教員試験よりも参考書や過去問の種類が豊富です。最新の情報を身につけるためにも、出版年の新しい教材を選んで勉強しましょう。
質問できる相手がいない
学習のなかでわからないことがあったとしても、それを質問する相手がいないために自分で調べて解決しなければなりません。
- 調べものに時間がかかり、試験対策が遠回りになる
- 正しい解答や認識を得られる確証がない
以上のようなリスクがあるのが独学のデメリットの1つといえます。
また、一緒にがんばる仲間が近くにいないため、モチベーションコントロールが難しいというのもデメリットに挙げられるでしょう。
SNS上で独学で日本語教師を目指す人達のコミュニティを形成するなどの工夫があるとよいかもしれません。
日本語教師養成講座によっては日本語教員試験の対策講座を開講している場合もありますので、スポットで受講するのも一つの手です。
授業の実践力がつきにくい
日本語教師養成講座を受講すると、講座で知識を習得するだけでなく、模擬授業をおこなう機会もあります。
この模擬授業において、実際に仕事を始めたときに活かせる実践的なスキルを数多く学ぶことができるのです。
しかし、独学ではその模擬授業の機会を得られないため、実践力がつきにくい傾向にあります。
また、採用試験の際に模擬授業や実習といった実践経験をもとにした回答がしづらい点も考慮しておきましょう。
以上のように独学の場合、メリット・デメリットがそれぞれあります。
自分に合った勉強方法を選ぶことが大切になります。
国家資格「登録日本語教員」が目指せるおすすめスクール
独学で勉強する方法とポイント
まず日本語教員試験の概要・全体像を把握する
試験対策を始める前に、まずは日本語教員試験の概要と全体像を把握しましょう。
日本語教員試験の大まかな内容は前述した通りですが、文部科学省の公式Webサイト(日本語教員試験に関すること)や日本語教員試験の公式Webサイトから最新情報を確認できます。
日本語教員試験実施要項や試験案内から、試験日程や出題範囲、試験時間などをしっかりと理解しておきましょう。
合格ラインを知っておく
勉強を進めるにあたって、あらかじめ合格ラインを知っておくことも大切です。出題範囲に対して必要な点数の目安がわかるため、勉強量や目標を決めやすくなります。
日本語教員試験の合格ラインは次の通りです。
- 基礎試験
- 出題内容の5区分でそれぞれ6割程度の得点かつ、総合得点8割程度
《参考:おおよその出題割合》
1、社会・文化・地域:約1~2割
2、言語と社会:約1割
3、言語と心理:約1割
4、言語と教育(教育実習を除く):約3~4割
5、言語:約3割 - 応用試験
- 総合得点で6割程度
基礎試験は5区分の出題割合も公表されています。「4、言語と教育」「5、言語」の割合が高いため、総合得点8割を目指すには力を入れて勉強したいところです。
ただし、各区分で6割程度の得点が必要になることや、応用問題は区分を横断して出題されることを踏まえると、まんべんなく5区分の勉強が必要です。
試験日から逆算して学習計画を立てる
独学で日本語教師の試験に合格するためには、試験日から逆算して学習計画を立てる必要があります。
なぜなら、出題傾向に合わせた学習計画を立てることによって、試験までの時間経過ごとに必要な勉強内容や学力を把握することができるからです。
さらに計画があることで、勉強の進捗も把握できるため、軌道修正も可能になるでしょう。
ただし、最初から完璧な学習計画を立てるのは難しいため、日次・週次で振り返りながら最適な計画に修正していきましょう。
具体的な計画を立てるのがポイント
学習計画を立てる際は、曖昧な計画にならないように注意しましょう。
効率的に勉強を進めるためには、大まかなスケジュールに沿って決めた学習内容を、毎日の学習内容へ落とし込みます。
「何を」・「どの参考書で」・「何ページまで」勉強するのかを具体的に決めることがポイントです。
学習期間とスケジュールの目安
日本語教員試験の出題範囲は、従来の日本語教師養成講座・日本語教育能力検定試験と同じであるため、同講座の受講時間である420時間がスケジュールの目安となるでしょう。
仮に1日の勉強時間を2時間とすると、「420÷2=210日=約7ヶ月」と計算できます。養成機関ルートの受講期間は6ヶ月から1年程度であるため、独学の場合も学習期間の目安は6ヶ月から1年程度で考えておくといいかもしれません。
11月の日本語教員試験に向けて、約6ヶ月で試験対策をする場合のスケジュール例は、以下の通りです。
- 6月:教材を使って基礎・基本を理解する
- 7月:問題演習に取り組み、基礎を固める
- 8月:過去問・サンプル問題を解き、間違えた問題を解説や参考書で確認、弱点を強化する
- 9月:過去問を解き、出題傾向をつかむ
- 10月:過去問を繰り返し解き、苦手分野の対策を重点的に行う
- 11月:総復習を行い、試験本番に臨む
尚、日本語教員試験は1年に1回以上とされているので、来年以降は1年に2回行われる年度もあるかもしれません。
まずは基礎・基本を理解する
いきなり問題演習に取り組むと、内容を理解するのに時間がかかったり、丸暗記になって類似問題に対応できる応用力が身につけられなかったりして、勉強効率が悪くなってしまう可能性があります。
そのため、まずは参考書などの教材を使って、日本語教育の基礎・基本を理解しましょう。
日本語教員試験の参考書は市販されているものが少ないため、日本語教育能力検定試験のテキストが役立ちます。試験範囲の区分ごとに整理された教材があると、自分の得意・苦手分野を理解できるのでおすすめです。
後述する書籍もぜひ活用してみてください。
関連記事 日本語教師資格が取得できる日本語教育能力検定試験とは?難易度や合格率、勉強方法について解説!
知識を定着させることがポイント
基礎知識を身につけてから問題に取り組むと、問題を通して参考書でインプットした知識をアウトプットすることができ、より記憶に定着しやすくなるというメリットがあります。
まずは参考書で基礎知識を学び、試験の全体像を把握してから問題演習に取り組みましょう。
過去問・サンプル問題を解いてみる
基礎知識を習得したら問題演習に取り組みましょう。
日本語教員試験は実施回数が少ないため過去問があまりありません。そこで、日本語教育能力検定試験の過去問でトレーニングを積みましょう。ただし、出題方法などは異なります。日本語教員試験の過去問・サンプル問題にもしっかり目を通して、試験対策をしましょう。
特に過去問を繰り返し解いていくと、試験の出題傾向や難易度、得意・不得意分野などについて把握をすることができます。
苦手分野は試験本番までに克服できるように、重点的に対策を行っていきましょう。
日本語教員試験のサンプル問題はWeb上に公開されており、誰でも閲覧可能です。ぜひチェックしてみてください。
また前述の通り、現時点では日本語教員試験の過去問がないので、代わりに日本語教育能力検定試験の過去問を解いていくと、いいトレーニングになるかもしれません。
参考 文部科学省「令和6年度日本語教員試験実施要項」、「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」、文化庁「日本語教員試験試行試験 結果の概要」
日本語教師を目指す方におすすめの書籍(本)8選!
ここからは、日本語教師を目指す方におすすめの書籍(本)を紹介していきます。
- 日本語教育の基礎をわかりやすく学べる
- 日本語教育能力検定試験対策ができる
以上の書籍8つをBrushUP学びがピックアップしました。独学を検討している方はぜひ参考にしてください!
(1)『日本語で外国人と話す技術』
[著者:高嶋 幸太著・出版社:くろしお出版]
著者は、立教大学兼任講師や早稲田大学非常勤インストラクターを歴任。専門は「教師教育」「第二言語習得」「海外日本語教育」です。
この書籍は、日本語を少し理解し、会話をすることができる外国籍の方と接する際に役立つ情報が書かれており、普段外国籍の方に対して日本語を教えている教師の目線で解説されています。
2つのポイントが学べる
外国籍の方に日本語を教える際に重要となる2つのポイントである、「どのような日本語を選択すればよいのか」と「楽しく日本語でコミュニケーションを取る際のポイント」を学ぶことができます。
さらに、わかりやすさを重視し、各項目は基本4ページ単位で構成されています。
日本語教育にあまり詳しくないという方の場合でも、やさしく読み進められる記述となっています。
(2)『日本語授業の進め方 生中継(日本語教師ハンドブック)』
[著者:金子 史朗・出版社:アルク]
日本語の授業の始め方から終わりまでを詳しく紹介している書籍であり、まさにこれから日本語教師を目指される方に適した内容となっています。
必要に応じて写真を使用していることに加え、一部の授業に関する知識は動画を利用しているのでわかりやすいでしょう。
初級レベルの23項目
「やりもらい」「自動詞・他動詞」などの、初級レベルといえる23項目が扱われています。
経験豊富な教師が、伝統的な授業の仕方に最新の手法をうまく組み合わせた、レベルの高い授業方法に関する知識を得ることができるでしょう。
期待できること
日本語教師に必要な内容がしっかりと詳しく説明されており、以下のことが期待できます。
・スピード感のある日本語の授業がどのようなものなのかが理解できる
・日本語教師にふさわしい話し方がわかる
・導入から活動までの授業の一連の流れがつかめる
・それぞれの授業での効果的な導入方法、すべきこと・すべきではないことを理解できる
・フラッシュカードや絵教材の見せ方がわかる
・すっきりと理解しやすい板書のしかたを会得できる
・効果的なプリント類のまとめ方がわかる
・授業時に教師が取るべき動作を理解できる
・日本語を教えている学習者から信頼されるコツを知ることができる
参考 Amazon 日本語授業の進め方 生中継(日本語教師ハンドブック)
(3)『Konnichiwa, Nihongo! こんにちは、にほんご!』
[著者:てくてく日本語教師会・出版社:ジャパンタイムズ]
日本語の教師グループが作った、見せて使える非常に便利な143ページの語彙・フレーズ集です。
イラストが適宜利用されていますが、オールカラーなので理解しやすいでしょう。
英中韓訳付きとなっていることも特徴です。
基本的なあいさつはもちろん、緊急事態に必要な表現まで、131のフレーズを学べるので、外国籍の方に日本語を教える際に役に立つ多くの知識を得られるでしょう。
長きにわたり好評
発売年は2009年と少し前になりますが、今でも好評の書籍です。
この事実こそが、内容が素晴らしいことの証明になるのではないでしょうか。
参考 Amazon Konnichiwa, Nihongo! こんにちは、にほんご!
(4)『いちばんやさしい日本語教育入門』
[著者:今井 新悟・出版社:アスク]
タイトルからも伝わりますが、理解のしやすさに力を入れた書籍となっているため、日本語教師でありながら、教え方にあまり自信がないという方にもおすすめです。
日本語教育に関する基本をしっかりと学ぶことができるでしょう。
特徴
特徴は以下のとおりです。
・簡単な語彙や表現が選ばれているのでスラスラと読める
・専門用語にはルビが付いている
・日本語教育の現場で使える知識が優先されている
・章ごとに確認問題がある
・Webで無料公開されている動画やPDFなどの資料にQRコードでリンクしている
やさしく書かれているのでわかりやすいと評判の書籍です。
(5)『もしも…あなたが外国人に「日本語を教える」としたら』
[著者:荒川 洋平・出版社:スリーエーネットワーク]
「教授法の実際」と「言語理論的な解説」との両面を掘り下げ、それらを反映させた書籍です。
突然外国籍の方に日本語を教えることになったという想定で進む内容のため、実際に日本語教師になった場合を具体的にイメージできるでしょう。
学べる内容
プロの教師ではないのに、日本語を教えることになってしまった主婦・会社員・日本人留学生の仮想体験を例としています。
日本語を外国語として教える方法について、複数の教え方や考え方を知ることができるでしょう。
また、日本語教育の基本的な事項である、語彙や音声などに加えて、コース・デザインや教室活動などについても網羅的に触れています。
日本語教師としてのステップアップの方法についての記載もあります。
この点も日本語教師を目指す方におすすめしたい理由です。
イメージしながら学びやすい
発売年は2004年ですが、この書籍から得られることは多いため、今もなお日本語教師を志す方たちから読まれ続けています。
どのようなやり方で教えるのかなどをイメージしながら読み進めていくことができるのが特徴といえるでしょう。
参考 Amazon もしも…あなたが外国人に「日本語を教える」としたら
(6)『日本語教育教科書 日本語教育能力検定試験 完全攻略ガイド 第5版』
[著者:ヒューマンアカデミー・出版社:翔泳社]
資格取得の総合校で有名なヒューマンアカデミーが送る、1冊で日本語教育能力検定試験を網羅できる参考書です。
都度リニューアルを重ねている参考書のため、最新の出題傾向に合わせた内容となっているのがポイントです。
独学でも試験合格が目指せる
「音声分野」「記述」問題も強力にフォロー。音声試験対策用にCDがついてきます。
また、実力をチェックできる演習問題もついてくるため、効率的に学びたい方におすすめの書籍といえるでしょう。
参考 Amazon 日本語教育教科書 日本語教育能力検定試験 完全攻略ガイド 第5版
(7)『令和3年度 日本語教育能力検定試験 試験問題』
[著者:公益財団法人日本国際教育支援協会・出版社:凡人社]
日本語教育能力検定試験主催の公益財団法人日本国際教育支援協会が出版する過去問題集です。
問題と解答のほか、その年度の試験実施状況(受験者数や平均点など)データが収録されているため、学習目標を立てる際の参考にもなる1冊です。
過去数年分の問題集を入手するのがおすすめ
こちらの試験問題集は、直近年度のほか、過去数年分の書籍について現在も販売されているものがあります。
試験内容を広く網羅するためにも、過去分の問題集にチャレンジすることが推奨されるでしょう。
参考 Amazon 令和3年度 日本語教育能力検定試験 試験問題
(8)『図表でスッキリわかる 日本語教育能力検定試験 合格キーワード1400』
[著者:泉 均・出版社:晶文社]
検定試験対策指導歴30年以上の著者が試験に出る必須キーワード1452語を厳選。
基本となる重要なキーワードと、それに関連するキーワードをコンパクトにまとめて解説している書籍です。
豊富な図表で視覚から覚えやすい
図表を用いて要点が簡潔にまとめられており、知識を整理しながら学習できることが特徴です。
辞書代わりとして活用できる書籍のため、日本語教師になってからも役立つ1冊でしょう。
参考 Amazon 図表でスッキリわかる 日本語教育能力検定試験 合格キーワード1400
自分に合った書籍を選ぶ!
日本語教育関連の書籍は上記で紹介したもの以外にも数多くあり、その特徴や内容はさまざまです。
自分に合った書籍選びが、日本語教師へのよい手引きとなるでしょう。
書籍を選ぶ際は、「説明がわかりやすいか、日本語教師になるイメージがわきやすいか」など、内容を確認・比較してみましょう。
養成機関の試験対策講座もおすすめ
「どこから勉強していいのかわからない」「学習内容について誰かに質問したい」「独学では難しそう」と思った方は、養成機関が実施している日本語教員試験の対策講座を検討してはいかがでしょうか。
養成機関の中には、国家試験対策に特化した講座を開講しているところがあります。養成機関ルートよりも受講料を抑えてプロの指導を受けられるため、経済的に養成機関ルートが難しい方にもおすすめです。
ただし、試験ルートには変わりないため応用試験の免除はありません。
以下で紹介する養成機関では、これまでの日本語教育能力検定試験・対策講座の経験を活かして、日本語教員試験の試験範囲を効率よく学べる講座を提供しています。
- 資格スクール大栄
- 日本東京国際学院
- アークアカデミー(通信・通学)
- ルネサンス日本語学院
まとめ
独学が難しい場合は養成機関ルートを検討してみる
先ほども説明したように、独学にはメリットもあればデメリットもあるため、自分で試験対策を進めるのが難しい場合は、養成機関ルートを選択するという手段もあります。
養成機関ルートでは、登録日本語教員養成機関で課程を修了し日本語教員試験の応用試験合格後(基礎試験は免除)、登録実践研修機関で実践研修を修了することで、日本語教師の資格が取得できます。
機関によっては、課程と実践研修を一体的に受講することも可能です。
養成機関ルートでは基礎試験が免除されるため、より確実に取得したい方にはおすすめのルートだと言えるでしょう。
旧制度で資格取得をした場合や、すでに日本語教師としての経験がある場合は、一定期間設けられている経過措置ルートを利用する方法もあります。
日本語教師の基礎が身につけられる書籍を読む
おすすめの書籍では、日本語教師を目指す方向けに仕事のイメージをつかむことができるものから、試験勉強に役立つものまで、幅広くあることがわかりました。
まずは、それぞれの本の特徴・内容を確認し、自分に合った書籍を選びましょう。
この記事が「日本語教師の仕事内容が気になる」方や「日本語教師の資格に興味があるけど、どのように勉強してよいかわからない」という方のお役に立つことができれば幸いです。
監修者プロフィール
早稲田大学名誉教授。言語・生活研究所代表。
現在は、言語・生活研究所の代表を務めながらオンラインでの日本語教育において精力的に活動中。
【主な経歴】
城西国際大学大学院人文科学研究科特任教授(2018/4~2019/3)
早稲田大学大学院日本語教育研究科専任教員(2002/4~2014/3)
早稲田大学日本語研究教育センター専任教員(1988/4~2002/3)
【代表著書】
『もう教科書は怖くない! 日本語教師のための初級文法・文型完全「文脈化」・「個人化」
アイデアブック』(ココ出版)(2016/12)
『ライブ! 成長する教師のための日本語教育ガイドブック』(共著)(ひつじ書房)(2005/5)
ほか多数
【海外派遣歴】
ケルン日本文化会館日本語教師オンライン研修会招待講師(2020/6)
EPA候補生・教師研修(ベトナム・ハノイ)招待講師(2020/2)
ほか多数








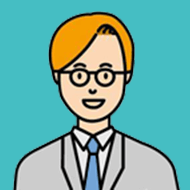
 受講料10%OFF!6万円分プレゼント特典付き!年末年始学習応援キャンペーン実施中(1月開催/全国)
受講料10%OFF!6万円分プレゼント特典付き!年末年始学習応援キャンペーン実施中(1月開催/全国)
 「日本語教師」の資格取得を目指すなら、38年超の実績を有するアークアカデミーで!
「日本語教師」の資格取得を目指すなら、38年超の実績を有するアークアカデミーで!
 【カナン東京日本語教師養成講座】学生を『主体的に』動かす・考えさせる『仕掛け』を考えよう
【カナン東京日本語教師養成講座】学生を『主体的に』動かす・考えさせる『仕掛け』を考えよう
 集まれ、未来の日本語教師!豊富な実習、徹底的な就職支援!説明会開催中!(夜間・土日も開催、高田馬場)
集まれ、未来の日本語教師!豊富な実習、徹底的な就職支援!説明会開催中!(夜間・土日も開催、高田馬場)






















 世界で最も取得されているNASMパーソナルトレーナーライセンスで、トレーナーになろう!!
世界で最も取得されているNASMパーソナルトレーナーライセンスで、トレーナーになろう!!
 動き出す人は、もう準備している。国家資格で差がつく1年へ!
動き出す人は、もう準備している。国家資格で差がつく1年へ!
 『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定





