社会福祉士が目指せるおすすめスクール
社会福祉士国家試験の合格率
社会福祉士国家試験の合格率は、かつて25〜30%台で推移していましたが、近年は大きく上昇しています
第37回(2025年実施)では、受験者数27,616名のうち15,561名が合格し、合格率は56.3%と、令和元年以降2番目に高い水準となりました。
この上昇の背景には、社会福祉士が福祉分野における高度な専門性を担う国家資格であることが関係しています。
試験は19科目群にわたり幅広い知識を問う内容で、総合的な理解力と実践的な問題解決能力が求められます。
さらに、近年は教育課程や出題内容の見直しが進み、学習支援環境も整備されてきたことが、合格率向上につながっていると考えられます。
大学・短大・専門学校等の合格率
4年制大学や短期大学、専門学校などの養成校(いわゆる「福祉系大学等ルート」「短期養成施設等ルート」「一般養成施設等ルート」)における社会福祉士国家試験の合格率は、全国平均(56.3%)を上回る傾向があります。
第37回(2025年度)試験におけるルート別の合格率(新卒者)では、福祉系大学等ルートが75.2%、短期養成施設等ルートが67.9%、一般養成施設等ルートが80.1%と、いずれも全国平均を大きく上回っています。
この高い合格率の背景として、養成校では国家試験の出題範囲に沿った体系的なカリキュラムが組まれており、理論的な基礎から実習まで段階的な学習が可能な学習環境が整備されています。特に実習科目を通じて現場での経験を通し理論と実務の結びつきを理解することで、試験の事例問題に対応する力が向上することが、合格率の上昇につながっていると考えられます。
通信制大学・養成施設の合格率
4年制大学や短期大学、専門学校などの養成校(いわゆる「福祉系大学等ルート」「短期養成施設等ルート」「一般養成施設等ルート」)における社会福祉士国家試験の合格率は、全国平均(58.1%)を上回る傾向があります。
第37回(2024年度)試験における新卒者の合格率を見ていきましょう。
| 福祉系大学等ルート | 76.8% |
| 短期養成施設等ルート | 68.0% |
| 一般養成施設等ルート | 80.7% |
いずれも全国平均を大きく超えています。
この高い合格率の背景には、養成校で国家試験の出題範囲に沿った体系的なカリキュラムが組まれていることがあります。
理論的な基礎から実習まで段階的に学べる環境が整い、特に実習科目を通じて理論と実務の結びつきを理解できる点が大きな強みです。
こうした学習プロセスによって事例問題への対応力が高まり、結果として合格率の向上につながっていると考えられます。
過去の社会福祉士の合格率推移と年度別データ
ここでは、過去の社会福祉士の合格率推移と年度別データに関して詳しく見ていきましょう。
直近5年の社会福祉士国家試験合格率推移
直近5年間における社会福祉士国家試験の合格率は、以下のように推移しています。特に2022年度以降、顕著な上昇が見られます。
| 2020年度(第33回) | 29.3% |
| 2021年度(第34回) | 31.1% |
| 2022年度(第35回) | 44.2% |
| 2023年度(第36回) | 58.1% |
| 2024年度(第37回) | 56.3% |
この推移を見ると、第30回から第34回までは合格率が30%前後で横ばいでしたが、それ以降は大きく上昇しています。特に第36回と第37回では、合格率が40%台から50%台へと一気に上がり、それまでの水準と比べて大きな変化が起きていることがわかります。
2020年〜2024年度の合格率・合格者数一覧
2020年度(第32回)から2024年度(第36回)までの社会福祉士国家試験における受験者数・合格者数・合格率は、以下のとおり推移しています。
| 2020年度(第33回) | 35,287人 | 10,333人 | 29.3% |
| 2021年度(第34回) | 34,563名 | 10,742人 | 31.1% |
| 2022年度(第35回) | 36,974人 | 16,338人 | 44.2% |
| 2023年度(第36回) | 34,539名 | 20,050人 | 58.1% |
| 2024年度(第37回) | 27,616名 | 15,561人 | 56.3% |
このデータを見ると、2020年度から2022年度までは合格率が30%前後で推移していましたが、2023年度以降は大幅に上昇しています。
特に2023年度には合格率が50%を超え、過去10年で最も高い水準となりました。
この背景には、試験制度や出題傾向の見直し、学習支援体制の整備など、さまざまな要因が影響している可能性があります。
今後予定されている2025年度試験の結果を踏まえることで、こうした傾向が一時的なものか、それとも長期的な流れなのかがより明確になるでしょう。
合格率が上昇・下降した年とその要因
社会福祉士国家試験の合格率は、制度改正や出題範囲の見直しによって大きく変動することがあります。
実際、2012年度(第24回試験)や2018年度(第30回試験)には新カリキュラムが導入され、受験者が新しい出題範囲に対応しきれず、一時的に合格率が低下しました。
一方、近年は状況が変わり、2020年度以降はむしろ合格率が上昇傾向にあります。
2022年度まではおおむね30%前後でしたが、2023年度には44.2%、2024年度には58.1%と大きく伸び、2025年度も56.3%と高い水準を維持しました。
この背景には、過去問対策の有効性が広く認識されていること、受験対策講座や通信教育の普及で学習環境が整ったこと、さらに出題傾向が安定してきたことが影響していると考えられます。
合格率から見る社会福祉士試験の難易度
社会福祉士国家試験の難易度を理解するうえで、合格率の数字だけを見て判断するのは適切ではありません。ここでは、以下の3つに関して解説します。
合格率を左右する合格基準点・得点分布
社会福祉士国家試験の合格基準は、原則として総得点の60%程度に設定された基準点に達することです。
ただし、年度ごとの試験難易度に応じて厚生労働省の試験委員会が基準点を調整する仕組みになっています。
そのため、問題が難しい年度は基準点が下がり、比較的やさしい年度は基準点が上がる傾向です。
さらに、総得点の基準を満たすだけでは不十分で、各科目群で原則として満点の半分以上を得点すること(いわゆる「科目ごとの足切り」)も条件に含まれます。
これにより、特定の科目だけに偏った学習では合格できない仕組みとなり、試験全体の公平性が保たれています。
介護福祉士・精神保健福祉士との難易度比較
社会福祉士試験の難易度を理解するには、他の福祉系国家資格と比較するのが有効です。
代表的な資格である介護福祉士や精神保健福祉士と比べると、社会福祉士は従来から合格率が低めであり、特に学習範囲の広さが際立っています。以下の比較表をご覧ください。
| 資格名 | 合格率(例年) | 主な特徴 |
| 社会福祉士 | かつては約30%前後だったが、直近では44〜58%(2023年度44.2%、2024年度58.1%、2025年度56.3%) | 出題範囲が広く、福祉制度・医学知識・心理学・法律など総合的な理解が必要。 |
| 介護福祉士 | 約65〜72% | 実務経験者が多く、日常業務の知識が試験に直結する。 |
| 精神保健福祉士 | 約55〜70% | 精神保健分野に特化した専門性が高い内容。 |
この比較からわかるように、社会福祉士は他の資格に比べて出題範囲が圧倒的に広く、複数分野にわたる総合力が求められるため難易度が高い資格です。
近年は合格率が上昇傾向にありますが、基準点や科目ごとの足切りを突破するには、計画的かつ継続的な学習が欠かせません。
社会福祉士国家試験の合格率が低い理由
社会福祉士試験の難易度を高めている要因として、まず出題範囲の広さが挙げられます。
福祉制度や心理学、医学、法律など多岐にわたる領域を学習する必要があり、効率的に計画を立てなければ全範囲を網羅するのは困難です。
さらに、受験者層の多様さも合格率に影響しています。大学生や社会人、実務経験者など背景が異なるため、準備時間や学習環境に差が生じやすいのです。
特に通信制課程の受験者は、仕事や家庭と両立しながらの学習になることが多く、計画性が合否を大きく左右します。
社会福祉士国家試験の合格率が変動する理由
社会福祉士国家試験の合格率は例年30%前後で推移していますが、年度によってわずかながら上下動があります。ここでは、なぜ合格率が変動するのかを解説します。
出題範囲・カリキュラム改正の影響
社会福祉士試験における合格率の変動要因として、出題範囲の広がりやカリキュラム改正の影響は非常に大きいといえます。
試験は社会のニーズに応じて制度や法律の改正内容を反映するため、新しい分野が追加される年度は受験者にとって大きな負担となります。
実際に、2012年度(第24回試験)には新カリキュラムの導入で出題範囲が拡大し、合格率は23.4%まで低下しました。また、2018年度(第30回試験)にもカリキュラム変更があり、受験者の準備が追いつかず合格率が下がっています。
こうした年度では、従来の教材や講座が改正内容に十分対応していなかったことも要因の一つといえるでしょう。
受験者層の変化
社会福祉士試験の合格率を左右する要因の1つに、受験者層の違いがあります。受験者には大学在学中の学生だけでなく、社会人や実務経験者も多く含まれています。
特に通信制大学や養成施設を利用する社会人の場合、仕事や家庭と両立しながら学習する必要があるため、十分な学習時間を確保しにくく、そのことが合格率に影響するのです。
これに対して、大学や専門学校に通う学生は体系的なカリキュラムに沿って学習を進められるため、比較的有利に試験へ臨める傾向があります。
新カリキュラム・教育制度の影響
社会福祉士試験の合格率に影響を及ぼす要因の1つが、新カリキュラムや教育制度の導入です。
養成課程の見直しによって実習内容や必修科目が増えると、学生の学習負担は大きくなり、準備が不十分な年度には合格率が一時的に下がる傾向があります。
実際、2012年度(第24回試験)では新カリキュラム導入の影響を受け、合格率は23.4%まで落ち込みました。
さらに2018年度(第30回試験)にも制度改正があり、合格率は26.2%と低水準にとどまりました。
これらの事例から、制度変更直後は受験者が新しい出題範囲に十分対応できないことがわかります。
社会福祉士国家試験の合格率を上げるための学習戦略
社会福祉士試験で合格を目指すためには、単に長時間勉強するだけではなく、効率的かつ戦略的な学習法を取り入れることが重要です。ここでは、具体的に合格率を上げるための学習戦略に関して解説します。
合格者が実践した勉強法と学習スケジュール例
合格者の学習法にはいくつかの共通点があり、特に「長期的な計画」と「直前期の集中」を組み合わせる方法が効果的です。
具体的には、試験日の半年前から全範囲のインプットを始め、過去問演習を中心に基礎知識を定着させます。そのうえで直前の1〜2か月は模擬試験や苦手分野の復習に集中し、得点力を底上げします。
学習時間の目安としては、平日は1〜2時間、休日は3〜4時間を確保する受験者が多いです。さらに過去問を繰り返し解くことで出題傾向を把握し、制限時間を意識した演習を積むことが実践的な得点力の向上につながります。
重要なのは、毎日の小さな積み重ねを継続することと、本番を意識した演習形式を取り入れることです。こうした学習の工夫によって、知識を得点へと結びつける力が強化され、合格に一歩近づけます。
通信講座・予備校・独学の特徴と最適な選び方
社会福祉士試験の学習方法には、通信講座・予備校・独学の3つがあります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、自分の学習環境や目的に合わせて選ぶことが大切です。
| 学習方法 | 特徴 | 向いている人 |
| 通信講座 | 自宅で学べ、添削指導や動画講義が受けられる | 忙しい社会人、計画立てが苦手な人、サポート体制を重視する人 |
| 予備校 | 講師から直接指導を受けられ、学習仲間も得やすい | 対面指導を重視する人、短期集中で学びたい人 |
| 独学 | 費用を抑え、自分のペースで進められる | 自律的に学べる人、基礎知識がある人 |
通信講座は、サポートを受けながら効率よく進めたい社会人に適しています。予備校は、集中できる環境や仲間との学習を求める受験生に有効です。一方、独学はコストを抑えられる一方で、自己管理力や情報収集力が不可欠となります。
最終的には、自分のライフスタイルや得意分野に合った方法を選ぶことが、効率的に合格へ近づくための鍵となります。
社会人受験者の時間術と集中法
社会人が社会福祉士試験に合格するためには、限られた時間をどう活用するかが大きな鍵となります。合格体験記でも多く挙げられているのは、「スキマ時間の活用」と「集中力の管理」です。
例えば、通勤や休憩の時間に短時間で復習できる教材を利用すれば、1日の総学習量を自然に増やせます。また、夜遅く疲れた状態で長時間勉強するよりも、朝の1時間を集中して学習する方が効果的だと感じる受験者も少なくありません。
さらに、ポモドーロ・テクニック(25分学習+5分休憩)を取り入れると集中力を保ちやすくなります。加えて、家族や職場の理解を得て学習時間を確保する工夫も大切です。
このように、社会人受験者は短時間でも質の高い学習を積み重ねることで、合格の可能性を大きく高められます。
社会福祉士の合格率に関するよくある質問
最後に社会福祉士の合格率に関するよくある質問に回答します。
社会福祉士の合格率はなぜ低いのでしょうか?
社会福祉士の合格率が低い主な理由は、出題範囲の広さと受験者層の多様性にあります。
試験科目は社会福祉制度や法律、心理学、医学など20科目以上にわたり、複数分野を横断的に学習しなければなりません。
2025年の社会福祉士国家試験はどうでしたか?
2024年度(第36回)の合格率は58.1%と過去より大きく上昇しました。合格者数も初めて2万人を超え、受験者動向の変化として注目されています。
社会福祉士になるのは難しいですか?
社会福祉士になるのは容易ではありません。しかし、計画的に学習を進め、継続して努力すれば、十分に取得を目指せる資格といえます。
まとめ:合格率の推移を踏まえ戦略的に学習しよう
社会福祉士国家試験は、かつて合格率が30%前後にとどまっていたため「難関資格」とされてきました。しかし直近では状況が変化し、2023年度は44.2%、2024年度は58.1%と、合格率は大幅に上昇しています。
とはいえ、試験範囲は福祉制度・心理学・医学・法律など20科目以上に広がっており、制度改正による出題内容の変化も避けられません。そのため、依然として学習負担の大きさが難易度を押し上げています。
大切なのは合格率という数値だけにとらわれるのではなく、その背景を理解したうえで自分に合った学習戦略を立てることです。過去問を徹底的に活用し、出題傾向を把握しながら、合格基準点を安定して超えられる実力を養うことが、合格への近道となります。




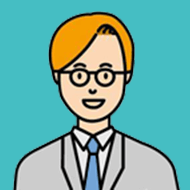
 児童福祉司が国家資格に!?厚生労働省が検討
児童福祉司が国家資格に!?厚生労働省が検討
 児童養護福祉士資格が新設!3月より認定講座開講
児童養護福祉士資格が新設!3月より認定講座開講











 資格取得 春の新キャリア取得応援!受講料10%OFF!早期申し込み6万円分プレゼント特典付き!
資格取得 春の新キャリア取得応援!受講料10%OFF!早期申し込み6万円分プレゼント特典付き!
 オンライン心理学教室4月開講! 実践に強い資格が取れるカウンセラー育成スクールが5月にスタート!
オンライン心理学教室4月開講! 実践に強い資格が取れるカウンセラー育成スクールが5月にスタート!
 『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
『キャリアコンサルタント国家資格説明会』首都圏、大阪、名古屋、仙台、札幌などの全国やオンラインで開催決定
 メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
メンタルヘルスの資格について詳しくわかる無料のイベント案内【新宿・銀座・横浜・名古屋・大阪・オンラインで開催】
 「日本語教師」の資格取得を目指すなら、38年超の実績を有するアークアカデミーで!
「日本語教師」の資格取得を目指すなら、38年超の実績を有するアークアカデミーで!





